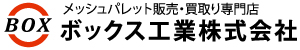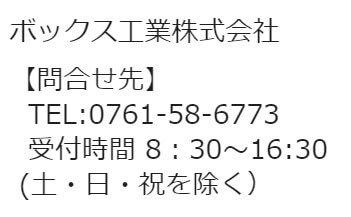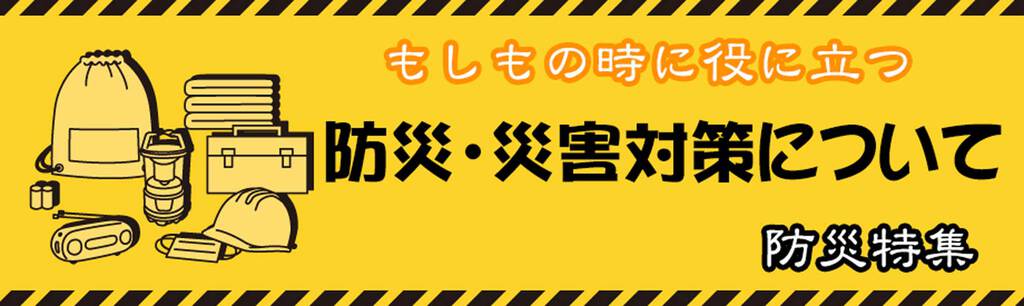
子どもと一緒に学べる防災教育アイデア
災害の多い日本で、子どもに本当に必要なのは知識の丸暗記ではなく、自分とまわりを守る行動スキルです。本特集は「たのしく・くり返し・家族で」を合言葉に、①習慣化 ②体験化 ③遊び化 ④家族化 ⑤地域化の5原則で設計。家庭・学校・地域でそのまま使える台本と教材アイデアをまとめました。
イントロ:防災を“科目”から“生活のスキル”へ
5つの設計原則
- 習慣化:小さく続けて定着させる(枕元セット、月1ミッション)
- 体験化:体を動かす訓練(しゃがむ・かくれる・まつ)
- 遊び化:ゲームや工作で楽しく学ぶ
- 家族化:役割分担と連絡ルールを紙で共有
- 地域化:近所の人・学校・町会とつながる
年齢別ロードマップ(目安)
幼児(3–6歳)
- 3つの約束:「あたまをまもる」「おとなのそば」「あんぜんカード」
- ごっこ遊び:机の下にもぐる→10秒カウント→「よし」で整列
- 触って学ぶ:懐中電灯・笛・非常用ブランケットを体験
小学校低学年(6–8歳)
- 家の安全さがし:倒れそうな家具に「キケン」シール
- 避難合図ゲーム:拍手1回=しゃがむ/2回=かくれる/3回=まつ
- ミニ工作:ペットボトルランタン(LED+アルミ反射)
中学年(9–10歳)
- ハザードマップ宝さがし:自宅→学校→公園ルートを色分け
- 防災クッキング:火を使わないツナマヨ丼
- 通信ドリル:家族連絡カード作成、171の体験(音声体験)
高学年(11–12歳)
- 家族の役割:防災キャプテン/連絡係/補給係
- 科学実験:ろ過の仕組み(学習用・飲用不可)
- 避難所ルールづくり:ゾーニング・静粛時間・衛生
中高生(13–18歳)
- プロジェクト学習:学校・自治体の訓練を企画提案
- メディア・リテラシー:一次情報の確認と拡散ルール
- ボランティア入門:物資仕分け・要配慮者支援の見学
家庭で回す「4週間ミニ・カリキュラム」
Week1:わが家の安全を知る
- 家の「危険さがし」マップ作り(家具・ガラス・通路)
- 枕元セット(スリッパ・ライト・ホイッスル)全員分
- 15分の夜間ミニ訓練:暗闇でトイレ往復
Week2:連絡と集合のルール化
- 家族連絡カード作成(一次・二次集合場所、合言葉)
- 家族チャットの緊急テンプレ、171の使い方を掲示
- 自宅・学校・職場の「避難三角形」地図を冷蔵庫に
Week3:食と衛生、暮らしの工夫
- ローリングストック棚卸し(水・缶詰・レトルト)
- お皿にラップ実験(洗い物削減)、ごみ分別の確認
- 携帯トイレの実物確認(仕組み理解)
Week4:まちとつながる
- 近所の一次避難場所まで実歩(雨天で“悪条件”体験)
- 町会・学校の訓練日をカレンダー登録、子ども役割を申し出
- 学びのふり返り:できた3つ/次にやる1つを掲示
学校・学童・PTA向け:90分ワークショップ設計図
目的と構成
目的:自ら判断し、仲間と助け合える初動スキルを身につける。
- 導入10分:身近な災害クイズ(○×カード)
- 体験30分:「しゃがむ・かくれる・まつ」動作→机上落下物シミュレーション
- 地図30分:学校〜自宅の安全ルート設計(危険×/安全◎/代替→)
- 共有20分:班発表→良い点にシール投票
- ふり返り10分:「今日の約束カード」に家庭タスクを記入
評価方法
- 「5分で出発」「集合場所を言える」など行動目標の達成チェック
ゲーム&アクティビティ18選(抜粋)
- 防災ビンゴ(家の中の安全対策をそろえる)
- 30秒持ち物レース(玄関から持ち出し袋を取って戻る)
- 防災ジェスチャー(“余震”や“停電”を身ぶりで伝える)
- 封印キッチン(水・火・包丁を使用しないレシピ)
- 避難MAPパズル(白地図に避難先ピースをはめる)
- 衛生王決定戦(石けん泡立てタイムアタック)
- 手作り簡易電池(ハンドメイド防災)
- 暗闇宝探し(懐中電灯で安全ルートを探す)
- 水運びリレー(ペットボトルで“こぼさず運ぶ”)
- 防災クイズ(参考事例)
- ポスター工房(避難所のマナー掲示物を作る)
- 新聞紙帽子ヘルメット(頭部保護・熱中症予防)
- 非常用袋詰め(自分にあった組み合わせを考える)
- 節水チャレンジ(1日4Lで生活プランを立てる)
- ベッドサイド点検(枕元の三種の神器:ライト・スリッパ・笛)
- “やさしさ係”(要配慮者の支援アイデアを出し合う)
STEAMで学ぶ:科学×ものづくり
- LEDライト工作(導通・極性)
- ろ過の仕組み観察(学習用・飲用不可)
- 気象観察ノート(毎日3分、台風期の変化)
- 簡易地震計模型(紙コップ+糸+ペン)
- タイマーで防災チェックを通知する簡易プログラム
多様性に配慮する設計
- 発達特性:視覚手順書、予測できるタイムテーブル、休憩コーナー
- 低年齢:手順を2〜3に分割、即時フィードバック
- 多言語:ピクトグラム&二言語カード、家庭内の通訳役を決定
- 身体特性:階段回避ルート、補助具チェックリスト
- 感覚過敏:耳栓・サングラス・フード付き衣類を避難キットに
防災クッキング(火を使わない3品)
- ツナコーンクリーム丼:ツナ+コーン+粉チーズ+マヨ→レトルトご飯
- 和風混ぜご飯:サバ水煮+めんつゆ+乾燥わかめ
- フルーツヨーグルト:缶詰+ヨーグルト(常温可)+クラッカー
※アレルギー表記を確認。衛生に留意し、試食は少量から。
15分・30分の“おうち避難訓練”台本
15分(平日夜)
- 合図(手拍子3回)→机下に集合
- ライトを持ち、靴を履く→玄関に整列
- 一次集合場所を声に出して確認→ふり返り
30分(休日昼)
- 停電想定でブレーカーOFF(安全確認の上)
- 家族連絡カードでメッセージ作成→合言葉を復唱
- 近所の避難路1本を歩行→帰宅後チェック記入
ふり返りと評価:やる気を持続させる仕掛け
- バッジ制度(地図名人/電池博士/衛生チャンピオン)
- 学習ログ:できた○・次の約束△を1分で記録
- 見える化:冷蔵庫に「今月のミッション」シール表
- 発表会:月末に家族ミニ発表(1人1分)
安全上の注意(大人向けメモ)
- 応急手当・CPRは講習で正規手順を習得
- 浄水・火の扱いは大人が管理(学習目的・飲用不可)
- 夜間歩行や訓練は近隣へ配慮、私有地立入禁止を順守
- 連絡カードの個人情報は撮影・公開しない
成果チェック(子どもと一緒に)
- 一次・二次集合場所を口頭で言える
- 家族連絡カードを自分で取り出せる
- 枕元にライト・スリッパ・笛を置けている
- 学校→自宅の安全ルートを1本説明できる
- ローリングストックを1品入れ替えた
- 避難所のマナーを3つ挙げられる
- 一次情報と二次情報の違いを説明できる
- 要配慮者への配慮アイデアを1つ言える
- 月1のミッション表に記入できた
- 家族訓練を2回以上実施した
付録アイデア(必要なら作成します)
- 家族連絡カード(合言葉・集合場所・緊急連絡)
- 危険さがしシール台紙/避難路白地図(自宅中心1km)
- おうち訓練台本(15/30/60分)
- バッジ台紙&ミッション表
まとめ:小さく、楽しく、くり返す
防災教育は「年に一度の行事」では定着しません。小さく始めて、楽しく、くり返す。今日の一歩は、家族連絡カードを作る、枕元セットを揃える、家の危険シールを貼る――どれでもOK。子どもが主体的に動けることが、最大の備えです。