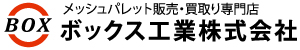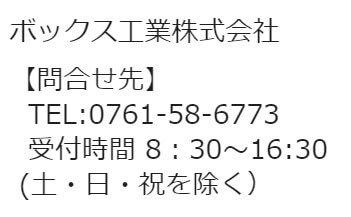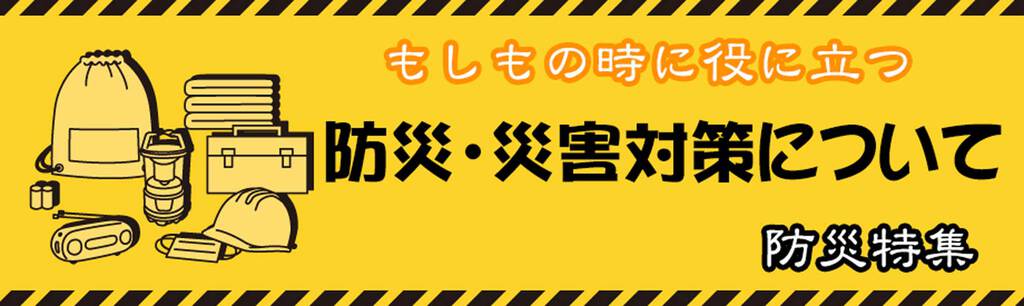
災害の種類別防災について(地震・台風・豪雨)
同じ「防災」でも地震・台風・豪雨は対処が異なります。本稿は①事前準備②発生時③初動72時間④復旧期で、災害別に最適化しましょう。
はじめに:災害は“種類ごと”に戦い方が違う
基本方針
まずは「命→健康→生活→資産」の順に守ることを軸に、行動を〈備える/守る/つなぐ/立て直す〉の4フェーズで設計する。まず家族全員が同じ判断基準を共有する。避難のトリガー(警戒レベル、家屋損傷、冠水深、土砂警戒区域入り等)を紙に書き、冷蔵庫や玄関に掲示。連絡は電話不通を前提に171・家族チャット・近所のキーパーソンの“三重線”で確保し、集合場所は一次(近所)と二次(広域)を決め、持ち出し袋を玄関動線に置いて「5分で出発」を徹底する。
備蓄はローリングストックで72時間から7日へ拡張し、水・食・電源・衛生・薬を人ごとにパッケージ化、住居内の複数箇所に分散。住まいは「ケガをしない家」に改造し、寝室と通路の安全最優先で家具固定・飛散防止フィルム・感震ブレーカー・足元灯・踏み抜き防止インソールを整える。情報は一次情報(自治体・気象庁・信頼メディア)と防災アプリを重ね受信し、オフライン地図を保存、停電想定でモバイル電源を常時満充電に。
移動は徒歩・車・公共の三様を想定し、川沿い・アンダーパス・崖下を避ける代替ルートを紙地図にも記す。職場・学校の引き渡しルールや帰宅困難時の合流方針も確認。復旧期に備え、保険と重要書類は耐火袋+クラウドで二重管理、被害は必ず写真で記録。片付けはPPEを着用し、撮影→仕分け→乾燥→消毒の順で。心のケアは情報接触を時間で区切り、睡眠・食事・排泄のルーティンを守る。最後に、半年ごとの総点検・月1品の補充・年2回の避難訓練で「備えを回す」。
共通編:すべての災害に効く“基礎体力”
家族ルール(5分で出発)
- 一次集合場所+広域避難先、災害用伝言ダイヤル「171」や家族チャット
- 避難トリガー(警戒レベル・損傷・冠水)を紙で明文化
備蓄(ローリング×ゾーニング)
- 水1人1日3L×最低3日(理想7日)を複数箇所に分散
- 火を使わず食べられる主食・たんぱく・間食をセット化
- 電源(モバイルバッテリー/乾電池/手回しラジオ)・携帯トイレ・救急セット
住まいの安全
- 家具固定・飛散防止フィルム・感震ブレーカーの検討
- 枕元/玄関/キッチンにライト、ベッド下にスリッパ
情報と地図(オフライン前提)
- 防災アプリ複数導入で“重ね受信”・生活圏のオフライン地図保存
地震編:突然“水平から垂直”の力が来る
事前準備
- 寝室と動線の安全最優先(家具固定・避難靴2カ所)
- Drop/Cover/Hold Onの家族訓練・重要書類は耐火袋+クラウド
発生時(屋内/屋外/乗り物)
- 屋内:頭部保護→机下→揺れ後にガス閉栓
- 屋外:塀・ガラス・看板から離れる/エレベーターは最寄階で降りる
- 車:左側停車・ラジオで情報・津波恐れは徒歩で高台へ
初動72時間
- 0〜10分:負傷確認・圧迫止血・火気確認
- 10〜30分:靴・ライト・水・モバイル電源確保、余震対策継続
- 30分〜3時間:近隣安否、インフラ点検、避難要否判断
- 3〜24時間:在宅ゾーニングor避難実行、戸締り
- 24〜72時間:復旧見込み確認、食水配分、情報は複数ソースで
二次災害と復旧
- 通電火災対策(ブレーカー遮断/再通電は立会い)・ガス漏れ換気
- 津波:弱い揺れでも高台へ、決して見に行かない
- 片付けはPPE着用・罹災証明は片付け前に撮影・保険/行政連絡
台風編:来襲前に“準備で勝つ”
72h/24h/6h前の段取り
- 72h:進路と暴風・大雨・高潮の想定、在宅勤務/休暇調整
- 24h:飛散物撤去・雨戸点検・水のう/土のう・車は高台へ
- 6h:冷蔵庫の保冷延長・浴槽に生活用水・家族の最終確認
接近中〜最接近
- 外出しない・窓から離れる・養生+二重カーテン
- 停電前提で電源と灯り集約・冷蔵庫開閉最小
- 海/河川/用水路へ近づかない・車移動は中止
住宅別ポイントと復旧
- 戸建:屋根/雨樋/アンテナ点検・固定
- 集合:ベランダ排水口の詰まり確認・共用部片付け
- 古木造:合板+養生テープで補強・室内は二重カーテン
- 復旧:倒木/電線/冠水路に近づかない、屋根応急は二人以上・命綱
豪雨編:ゆっくり来て“急に危険”
事前確認
- ハザードマップで洪水/内水/土砂の把握、複数の避難経路
- 警戒レベルの意味共有(レベル3で高齢者等は避難開始)
降り出してからの判断
- 水平避難:明るい・未冠水・移動可能時/垂直避難:冠水/夜間/移動危険
- 地下施設から早期離脱、マンホール浮上に注意
車と水の危険・復旧
- 冠水路へ進入しない(見た目より深い/路面欠損/流速)
- 復旧はPPE着用、乾燥→消毒→再乾燥、感染症に注意
横断トピック:誰も取り残さない防災
要配慮者(高齢者・障害・妊産婦・乳幼児)
- 薬14日分・オフラインでも機能する服薬アラーム
- 階段回避ルートの実踏・補助者の役割表を紙で
- 母子用品はスティック粉ミルク等で衛生的に
ペット同行避難
- 受入条件の事前確認、フード/水/トイレ/証明書、クレート訓練
住まいと保険・学校/職場
- 耐震診断、保険(地震・水災)見直し、家財写真の台帳化
- 帰宅困難を前提にオフィス備蓄、学校の引き渡しルール共有
よくある誤解と正解(Myth-Busters)
- ×窓に×印で割れない → ○飛散防止フィルム+二重カーテン
- ×冠水は膝までOK → ○流速・マンホールで転倒/吸い込み危険
- ×停電中は冷蔵庫を頻繁に確認 → ○開閉最小で温度維持
- ×津波は一度で終わる → ○複数回到達、見に行かない
片付け・衛生・心のケア
PPEと作業手順
- ヘルメット/ゴーグル/厚手手袋/踏み抜き防止
- 撮影→仕分け→搬出→洗浄→乾燥→消毒→再乾燥
メンタルヘルス
- 睡眠・食事・排泄のルーティン化、情報接触は時間で区切る
- 罪悪感や怒りは正常反応、早めに相談先へアクセス
巻末チェックリスト(保存版)
A. 5分で持ち出す
- スマホ/モバイル電源/現金/鍵/身分証コピー、水500mL×2・栄養バー×2、ライト、携帯トイレ×3、マスク/ウェット/ポリ袋/軍手
B. 在宅72時間キット
- 飲料水9L以上/人、主食・缶詰、カセットコンロ/ボンベ、紙皿・ラップ、カイロ、アルミブランケット、ラジオ、乾電池
C. 家庭内“安全3点”
- 寝室(落下物ゼロ/飛散防止/足元灯)・キッチン(ラッチ/耐震)・玄関(持ち出し袋/ヘルメット)
D. 家族ルール・テンプレ
- 集合場所/171伝言グループ/避難判断(レベル3/4)/ペット受け入れ避難所
まとめ:災害種別×フェーズ別で“勝ち筋”を作る
地震は突発=家具固定と初動10分、台風は予告型=72h段取り、豪雨は局地的急変=地図と警戒レベルで早動き。今日、水を3本追加・集合場所を紙に・アプリを2つ入れる――この一歩から始めましょう。