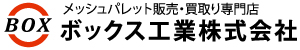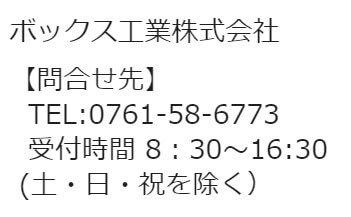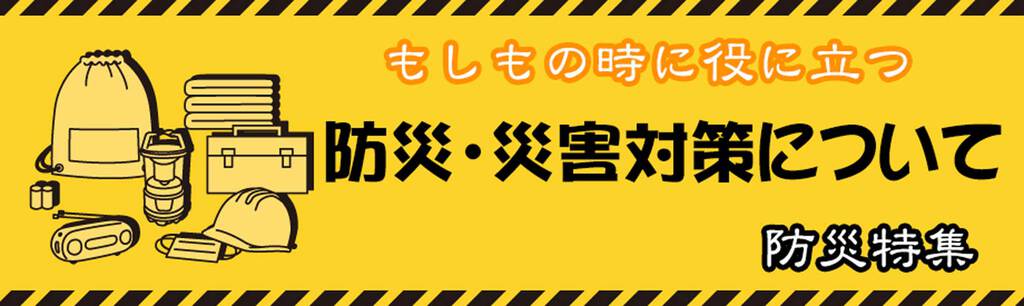
高齢者世帯のための防災対策と見直しポイント
高齢者世帯は、移動の負担や慢性疾患の服薬、視聴覚の低下、停電時の医療機器依存など、一般世帯とは異なるリスクを抱えています。だからこそ「ふつうの備え」をそのまま当てはめるのではなく、体力・持病・住環境に合わせて調整することが重要です。本記事では、今日から始められる実践策と定期見直しのポイントを整理します。
1. 基本方針:続けやすさを最優先
重い物・取り出しにくい配置は継続の敵。平時の生活動線に沿って置き場所を決め、半年に一度の見直しをカレンダー登録して習慣化しましょう。
運用のコツ
- 「玄関=持ち出し」「寝室=ライト/スリッパ」「キッチン=水/食料」とゾーニング
- 家族や支援者が見ても分かるラベリング(大きな文字)
2. 命をつなぐ備蓄:噛みやすく、開けやすく
備蓄の目安
- 水:1人1日3L × 最低3日分(可能なら7日分)
- 食品:やわらかご飯、ゼリー飲料、栄養補助バー、個包装パン・ビスケット等
高齢者向けの選び方
- 歯や義歯の状態に合う「嚙み切りやすい」もの
- 手の力が弱くても開けやすいプルトップ・易開封パウチ
服薬・補助具の継続
- 処方薬1〜2週間分+お薬手帳/処方内容のコピー
- 義歯ケース・洗浄剤、予備眼鏡、補聴器の電池(型番メモ)
3. 情報と電源:停電でも“つながり”を切らさない
電源の確保
- 大容量モバイルバッテリー
- 手回し/乾電池式ラジオ(通信断絶時の情報源)
情報入手と設定
- 緊急速報・防災アプリの通知ON、フラッシュ通知の活用
- 家族・支援者の連絡先は大きな文字でカード化し携帯
4. 住まいの安全化:転倒・転落・出火を防ぐ
転倒・転落対策
- 段差解消、手すり設置、滑り止めマット、夜間の足元灯
- タンス・本棚のL字金具固定
火災・ガラス対策
- ガラスの飛散防止フィルム
- 消火器・火災警報器の点検
酸素濃縮器など医療・介護機器を使う場合は、代替電源の確保先や避難受け入れ先をケアマネ/自治体と事前に確認・リスト化。
5. 避難計画:避難所と在宅、二本立て
避難先の下見
- 近隣の指定避難所のバリアフリー状況、トイレ、エレベーター有無を確認
- 階段回避ルートを実地で歩き、所要時間を把握
在宅避難の判断基準
- 家屋損傷の程度/断水・停電の見込み/薬の残量
支援体制の共有
- 避難支援者(近所のキーパーソン、民生委員、ケアマネ)の連絡先を玄関内側に掲示
- 合鍵の預け先や取り決めを家族と共有
6. 持ち出し品:軽く、小分けで、迷わない
配置と重量
- 持ち出し袋は5kg以内を目安に、玄関または寝室ドア付近へ
- 杖・歩行器とセットで掴める位置に固定
中身の例
- 500mL水×数本、ゼリー飲料、ソフトクッキー
- 処方薬1週間分、お薬手帳コピー、義歯用品
- 眼鏡/補聴器電池、携帯トイレ、ウェットティッシュ、マスク
- アルミブランケット、薄手ダウン/ポンチョ、カイロ
- 懐中電灯+ヘッドライト、ホイッスル、手袋
- 現金(小銭多め)、身分証・保険証のコピー、緊急連絡カード
開けやすさの工夫
- ファスナーに大きめタグ、薬は1回分ずつ小分け
7. 見守りと安否確認:孤立を防ぐ仕組み
連絡線の二重化
- 家族連絡(電話/LINE)+ご近所・町内会・民生委員で二重化
- 「地震後15分で安否連絡/返信なければ隣人が声かけ」などルールを紙で共有
救急情報シート
- 持病・服薬・主治医・家族連絡先を記したシートを冷蔵庫/玄関に掲示
8. 見直しポイント:季節・体調・住環境で更新
更新のタイミング
- 季節替わり:衣類・カイロ・熱中症対策品の入れ替え
- 体調変化:薬剤・介護用品の更新、荷重の再調整
- 住環境の変化:引越し・リフォーム時に避難経路と合鍵を再確認
維持する仕組み
- スマホに半年ごとの総点検、毎月1品のローリング補充をリマインド登録
まとめ
高齢者世帯の防災は、軽く・取り出しやすく・続けやすくが合言葉。備蓄・電源・住まいの安全化・避難計画・見守り体制の5点を押さえ、定期的に見直す仕組みを作ることが最大の防御になります。完璧を目指すより、今日ひとつ見直す――その積み重ねが、命を守る力になります。